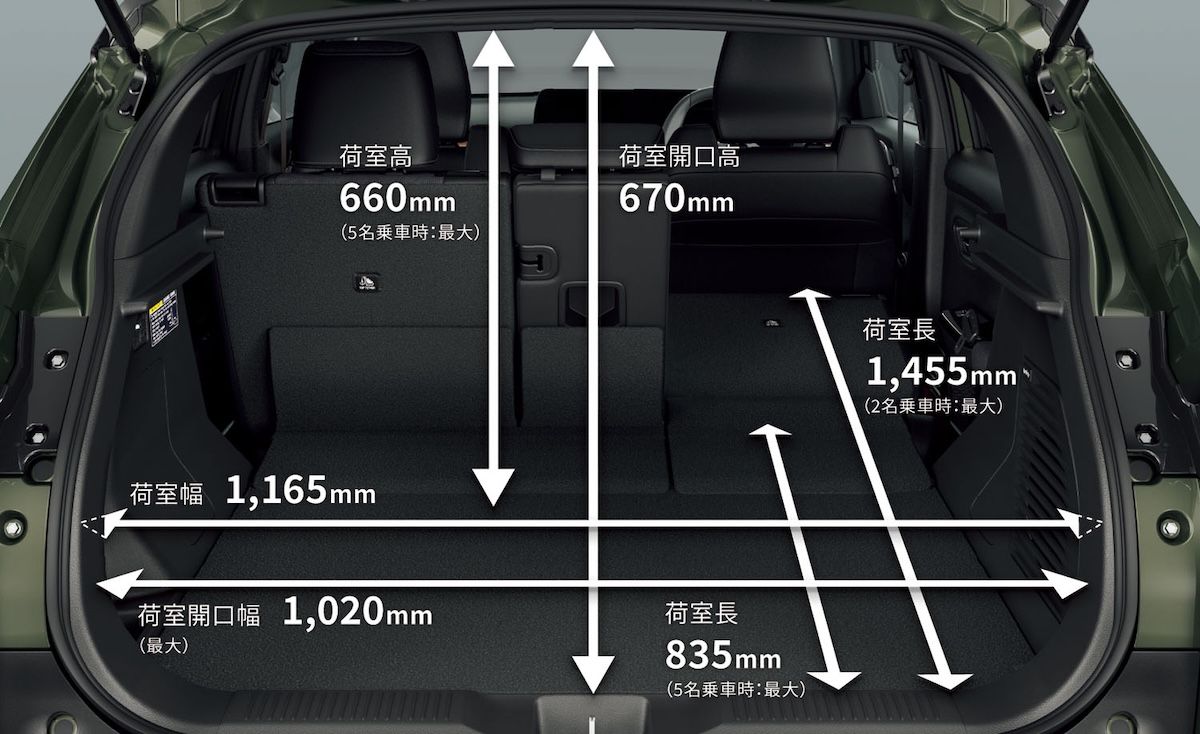ついにスズキがEV市場に殴り込みだ。初の電動SUV「eビターラ」は、コンパクトな扱いやすさと本格SUVの走破性を両立し、走りも価格も妥協なし。EVを特別視せず、あくまでスズキらしい一台として開発された挑戦者が、BセグメントEV市場に新風を巻き起こす!
実質311万円から手に入る本格コンパクトEV
9月16日、ついにスズキがEVの扉を開けた。その名は「eビターラ」。同社にとって初のバッテリーEVであり、SUVらしい力強さと扱いやすいコンパクトさを兼ね備えた一台だ。2024年のミラノでの初公開に続き、インドの巨大イベント「バーラト・モビリティ・グローバル・エキスポ2025」で世界に披露されたあと、いよいよ日本市場に乗り込んできた。言わば、スズキの次の世代を背負うグローバル戦略車の第一弾だ。

日本で展開されるのは3グレード。その仕様は、X(2WD/49kWh/航続距離433km)が399万3000円、Z(2WD/61kWh/航続距離520km)が448万8000円、Z(4WD/61kWh/航続距離472km)が492万8000円。いずれも「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象となり、87万円が交付される。つまり、最も手頃なXグレードは、実質311万円から購入できる計算となる。

EVの先進性とSUVの力強さを両立
コンセプトは「Emotional Versatile Cruiser(感情を揺さぶる多用途なクルーザー)」。少々、大げさに聞こえるかもしれないが、目の前のクルマを見ると不思議と納得できる。フロントマスクは押し出し感が強く、ショート・オーバーハングのプロポーションや大径タイヤは、小柄なボディながら、力強く山道を駆け上がるような雰囲気をまとっている。加えて、先進的な3ポイントLEDシグネチャーランプや空力と軽量化を両立させた18インチ・ガーニッシュ付きアルミホイールが、見た目にも新しい息吹を与えている。

インテリアは黒とブラウンを基調に、SUVのタフさと上質さを巧みに同居させた。10.25インチのメーターディスプレイと10.1インチのセンターディスプレイをひとつの面に収めた「インテグレーテッドディスプレイシステム」は、未来の計器盤をのぞき込んでいるようだ。さらにアンビエントライトやソフトパッド、ピアノブラック加飾など、細部までこだわりが光る。


走りで示すスズキDNA
「EVである前にクルマとしての基本性能を磨き上げました」と語ったのはチーフエンジニアの小野純生氏。日本のテストコースにとどまらず、欧州を含む世界各地で走り込みを重ねたという。

その心臓部はモーターやインバーターを一体化した「eAxle」。走行モードは「NORMAL」「ECO」「SPORT」に加え、アクセルひとつで加減速をこなす「イージードライブペダル」も備える。そして特筆すべきは前後に独立モーターを配した電動4WD「ALLGRIP-e」。路面状況に応じて制御を最適化する「オートモード」、さらに片輪が浮いた状況からも脱出できる「トレイルモード」を備え、雪道や悪路でも力強く突き進む。
私は実際に、袖ヶ浦フォレストレースウェイでこの4WD仕様のプロトタイプに試乗したが、「SPORT」モードでの加速は衝撃的だった。クルマが地面を一気に蹴り出すような力強さと、緻密に制御された安定感は非常に感心させられた。
さらに、骨格にはBEV専用に新開発された「HEARTECT-e」プラットフォームを採用。軽量で高剛性な構造に加え、高電圧部品の保護や広い室内スペースも確保する。大径タイヤを履きながら最小回転半径は5.2mと扱いやすく、日常の取り回し性能にも抜かりはない。
進化し続けるSDV、それでも堅実なOTA戦略
今回のeビターラは、スズキの世界戦略車であると同時に、SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)の第一弾でもある。販売後もソフトウェア更新で進化を続けるクルマだ。


ただし、すべてをOTA(オーバー・ザ・エア:無線ネットワークを用いたソフトウェア更新や機能追加)に任せたわけではない。「地図など必要な機能はOTAで対応しますが、それ以外はあえて非対応にしました。何でもかんでもではなく、安全性と分かりやすさを優先しています」と小野氏。スズキらしい堅実さがにじむ。
価格についても、鈴木俊宏社長は「補助金頼みではなく、持続可能な価格にしました。販売現場からも好意的に受け止められています」と語った。営業本部からは「既存のBセグEV(月100台規模)を超える販売を目指す」との声もあがった。
安心を支える販売網と充電インフラ
ブランド初のEVということで、サポート体制にも工夫がある。同社が取り入れるコネクト店制度がキモで、認定店であれば直営店と同等の情報やサポートを受けられる仕組みだ。販売スタッフには徹底したEV研修を施し、初めてEVを検討するユーザーにも安心を届ける。
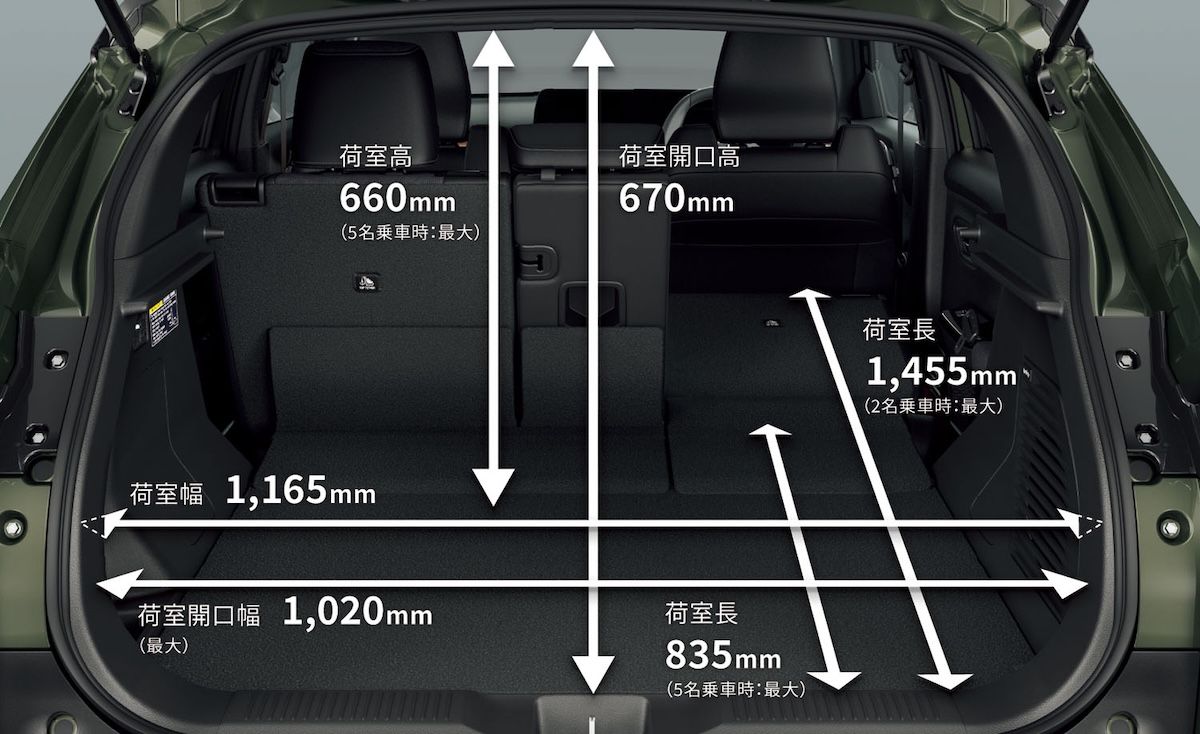
充電インフラは急速充電器を約100店舗、普通充電器を約800店舗に設置済み。専用アプリやカードにも対応予定で、日常の使い勝手を地道に高めている。
また、先進安全装備として衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、「サポカーSワイド」にも適合。国交省認定の「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」にも対応している点は注目だ。
「特別視しないEV」というスズキ流
鈴木社長が繰り返したのは「EVを特別視しない」という姿勢だった。「内燃機関車から自然に乗り換えられる存在にしたい。特に4駆設定は雪国や山間部での需要を意識しています。将来的には軽EVが普及の主役になるでしょう」。つまり、EVの未来を押しつけるのではなく、日常の延長線上に置く、それがスズキ流なのだ。
文・写真=佐藤 玄(ENGINE編集部)
(ENGINE Webオリジナル)